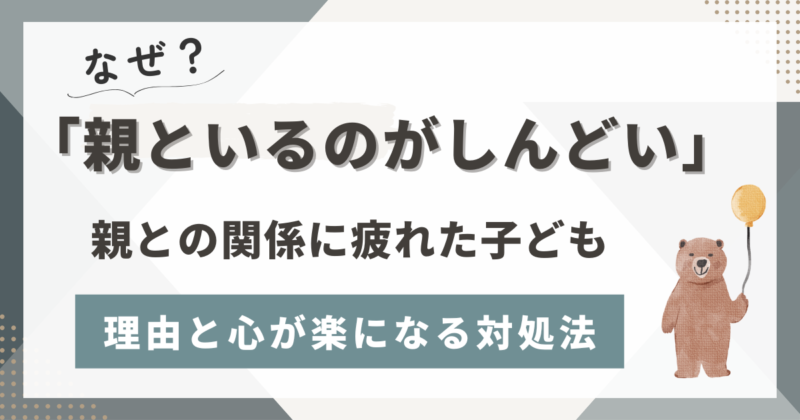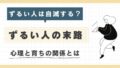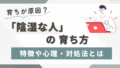当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
「親を大事にしなきゃ」と思いながら、親と関わると心がしんどい。
そんな”優しさ”と”しんどい気持ち”の間で、心が疲れていませんか?
「親といるのがしんどい」という気持ちに、親に対して罪悪感を抱き、「自分が冷たいのかも」と責めてしまっているかもしれません。
しかし、親との関係に疲れてしまったと感じるのは、あなただけの悩みではありません。
私も、親との関係に疲れたひとりです。
この記事では、生きづらさに悩み心理学を学んだ筆者の視点から、「親といるのがしんどい」と感じる理由を整理しつつ、心を守るために“やめてもいいこと”を7つ紹介します。
あなたが少しでも生きやすくなるきっかけになれば幸いです。
ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。
「親といるのがしんどい」と感じる理由とは?
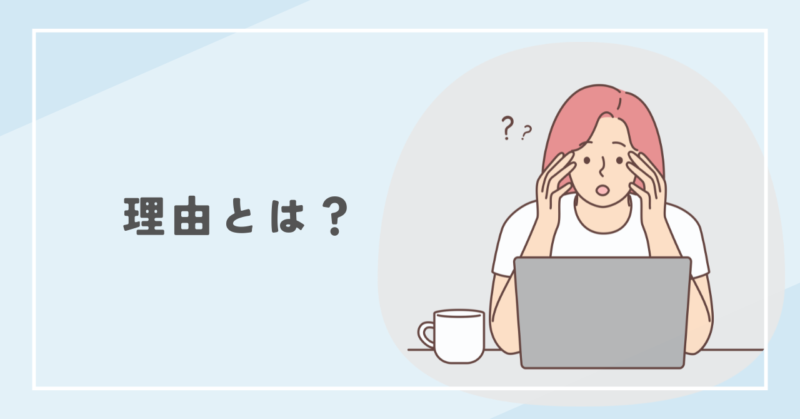
「親といるとしんどい」と感じるとき、「自分が冷たいのでは?」「親不孝なのでは?」と罪悪感を抱いていることが多いです。
しかし、心理学的に見ると、それは自然な感情であり、誰にでも起こりうることなのです。
親子関係には特有の「距離感の難しさ」や「幼少期からの影響」がからんでおり、それが心の負担につながっています。
親子関係は「距離感」が難しい
親子は、もっとも身近な存在である一方で、他人以上に距離感の調整が難しい関係です。
たとえば、親が「あなたのため」と言って口出ししてきても、子どもにとっては「干渉されている」と感じることがあります。
反対に、親が距離を取りすぎると「愛されていないのでは」と不安になってしまうこともあります。
心理学では、親子関係の距離感の取り方は、その後の人間関係にも影響すると考えられています。
適度な距離が取れないと、
と、感じやすくなるのです。
無意識に「子どもの頃の役割」を引きずっている
子どもの頃に家族の中で担っていた役割は、大人になっても無意識のうちに続いてしまうことがあります。
たとえば、
こうした役割を子どもの頃からずっと担ってきた人は多いのではないでしょうか。
役割を背負い続けると、大人になっても親の前で気を張ってしまい、
と、感じやすくなります。
自分でも気づかないうちに親との関係に縛られてしまっているのです。
「良い子でいなければ」という思い込み
「親に迷惑をかけてはいけない」「親を悲しませてはいけない」といった思い込みは、多くの人が心の奥に持っています。
これは、幼少期に親から繰り返し言われた言葉や、家庭の雰囲気の中で形成されることが多いものです。
つまり、
と、条件付きでなければ親に愛してもらえないと信じてしまう状態です。
こうした考え方は、大人になっても無意識に自分を縛り、
というパターンにつながります。
その結果、「親と一緒にいるとしんどい」という感覚をどんどん強めてしまうのです。
こちらの記事↓では、幼少期から親の期待に応えようとしてきた長女のつらさについて、詳しく解説しております。
親との関係に疲れたら「やめてもいいこと」7選
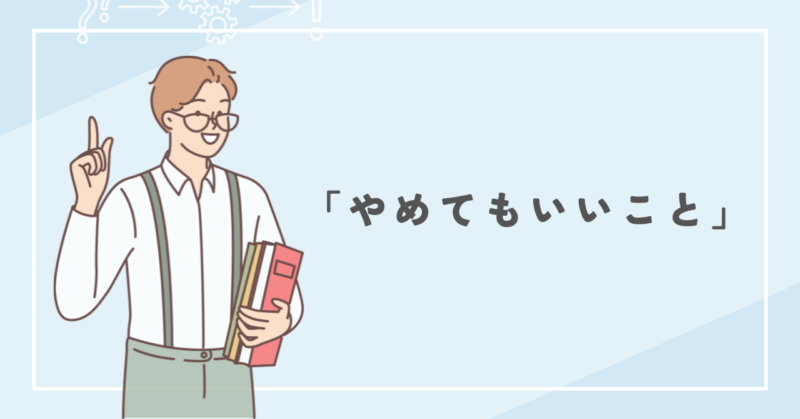
親との関係に疲れたと感じるとき、意識したいのは「やめてもいいこと」です。
これらを「してはいけない」と思い込む必要はありません。
むしろ、それをやめることで心が軽くなり、あなたらしい人生を取り戻せるのです。
いい子をやめてもいい
親の期待に応えようと「いい子」でい続けるのは、子どもの頃には必要だったかもしれません。
しかし、大人になってまで親の期待を優先し続けると、自分の気持ちや人生を犠牲にしてしまいます。
親に褒められるために完璧を目指すのではなく、
という感覚を持つことが大切です。
多少失敗しても、親の理想通りでなくても、あなたの価値は変わりません。
我慢しなくていい
そんな習慣が身についている人も多いでしょう。
しかし、その我慢が積み重なると、心は少しずつ疲れていきます。
小さなことでも、
と言葉にするだけで、心の負担は軽くなります。
我慢を手放すことは、親との関係を壊すことではなく、自分を守る健全な方法なのです。
無理に話を合わせなくていい
親の意見や価値観に、いつも「そうだね」と同調していませんか?
これは、親に否定されることを恐れて、自分の気持ちを押し殺してしまう状態です。
しかし、「話を合わせる=愛される」ではありません。
どんなに合わせても、親の支配的な態度が変わらないことも多いのです。
親が一方的に話してきたら、無理に共感する必要はありません。
だけでもいいのです。
あなたの心をすり減らすような会話から、少し距離を置く行動をしてみましょう。
親の機嫌をとらなくていい
というクセを持っている人は少なくありません。
しかし、親が不機嫌になるのは親自身の問題であり、あなたの責任ではありません。
たとえ親が怒っても、それをすべて自分のせいだと背負う必要はないのです。
機嫌を取ろうと無理をするよりも、
と切り分けることで、心はずっと自由になります。
こちらの記事↓では、親の機嫌取りに疲れた子どもの苦しみについて、詳しく解説しています。
許さなくてもいい
と、無理に許そうとしていませんか?
しかし、”許すこと”と”距離を取ること”は別です。
心理的には、「許す=関係を続ける」と誤解している人が多いですが、実際には「理解したうえで距離を置く」選択もあります。
親の言動によって、傷ついたり悲しい思いを繰り返してきた場合、親だからという理由だけで簡単には許せないでしょう。
無理に許そうとすると、再び傷つけられるリスクもあります。
あなたの心がまだ癒えていないなら、許す必要はありません。
まずは、
ことを最優先にしてください。
それが、あなた自身を大切にするということに意識を向けてください。
連絡を返さなくてもいい
そう感じて無理に関わっていませんか?
これは、罪悪感によって心が親に支配されている状態です。
親を優先して自分を後回しにする状態が続くと、慢性的なストレスになります。
連絡や帰省の頻度は、“常識”ではなく“あなたの心の余裕”で決めていいのです。
たとえば、
でも十分なのです。
「距離を取る=冷たい」ではありません。
これは、「自分の心を守る境界線を引く」という行動です。
親から逃げてもいい
と思い込んでいませんか?
しかし、限界を感じたら、物理的にも心理的にも距離を取ることは勇気ある選択です。
別居や連絡を取るのをやめるなど、あなたが心地よいと感じる距離を作ることは、自分を守るために必要なことです。
逃げることは「悪いこと」ではなく、
なのです。
あなたが元気でいることが、長い目で見れば親との関係を保つ力にもなります。
「親といるのがしんどい」と感じる親の特徴4選
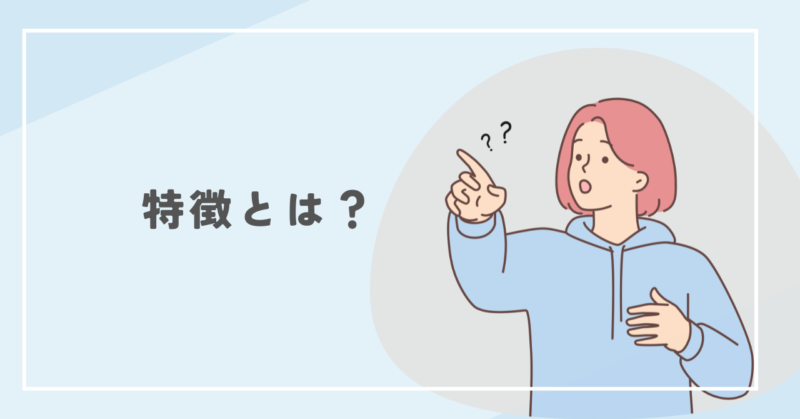
「親といるのがしんどい」と感じる背景には、親の性格や言動が関係しています。
すべての親が悪意を持っているわけではありませんが、子どもにとっては大きなストレスになりやすい行動があるのです。
ここでは代表的な親の特徴を紹介します。
否定的な言葉が多い親
子どもの話を聞いても、
と、否定的な言葉を返す親です。
こういった言葉を繰り返されると、子どもの自己肯定感はどんどん下がっていきます。
大人になってからも「親に話しても否定される」と身構えてしまい、一緒にいるだけで疲れやすくなるのです。
過干渉・支配的な親
など、親の価値観を押し付けてくるタイプです。
これは、親が子どもを心理的にコントロールしている状態で、子どもは自分で意思決定する力を奪われてしまいます。
自分の人生を歩もうとしても「親の顔色を見なければ」と感じてしまい、息苦しさを抱えやすくなるのです。
こちらの記事↓では、なんでも干渉してくる「心配性の親」の対処法について、詳しく解説しています。
被害者意識が強い親
など、自己犠牲をアピールしたり、つねに不満を口にする親です。
こうした親の態度は、子どもに「罪悪感」を植え付けます。
子どもは、親のことを「自分を傷つける人」だとは考えないので、親の不満の原因は自分なのではないかと考えてしまうのです。
子どもは「自分がもっと頑張らなければ」と感じてしまい、結果的に心が疲れ切ってしまいます。
世間体を優先する親
と、つねに外からの評価を気にする親です。
このタイプの親は、子どもの気持ちより「周囲にどう見られるか」を優先します。
子どもは「自分の気持ちは尊重されない」と学習し、やがて「親の前では本音を出さないほうが安全」と思うようになります。
これが長く続くと、親と一緒にいる時間そのものがしんどくなってしまうのです。
こちらの記事↓では、「ダメな親」に育てられた、子どもの本音や心の葛藤について、詳しく解説しています。
「親といるのがしんどい」と感じるのは悪くない
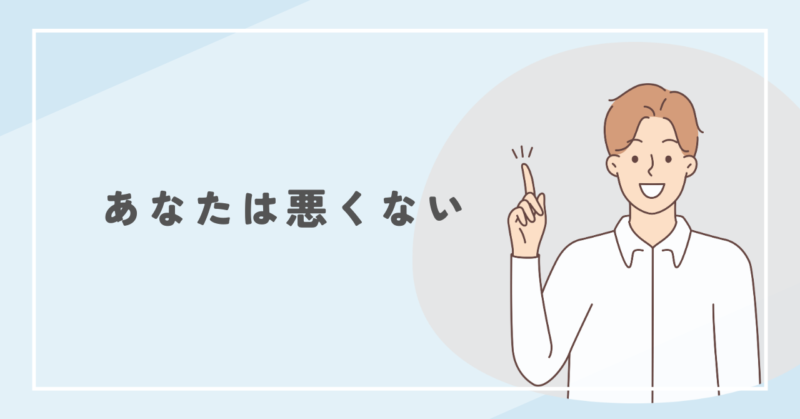
親に対して「一緒にいると疲れる」と感じると、多くの人は「自分が冷たいのでは」と罪悪感を抱きます。
しかし心理学の視点から見ると、これは決して異常なことではありません。
むしろ自然な感情であり、心が「これ以上は無理」「休みたい」と知らせてくれているサインなのです。
「親といるのがしんどい」は自然な感情
親子関係は一生続くもので、他の人間関係よりも距離がとても近いです。
そのため、他人からなら聞き流せる一言でも、親から言われると深く傷ついてしまうことがあります。
たとえば、親に、
と否定されると、自分の価値を強く揺さぶられるように感じるのです。
心理学的には、この「しんどい」という感覚は防衛反応です。
自分の心を守るために「これ以上はつらい」と体が教えてくれているサインであり、わがままでも異常でもありません。
子どもの頃の習慣が残っている
幼少期に「否定されやすい環境」や「親の顔色をうかがう環境」で育つと、子どもは無意識のうちに 自分を守るための反応を身につけます。
たとえば、
などの行動です。
こうした行動は、子ども時代には必要な“生き抜くための工夫”だったのかもしれません。
しかし、大人になった今でもその習慣が残っていると、「親といるとしんどい」という感覚につながってしまうのです。
親との関係に悩んでいる人は多い
「親といるのがしんどい」と感じているのは、あなただけではありません。
実際にカウンセリングや心理相談の場でも、親との関係に悩んでいる人は非常に多くいます。
という声はめずらしくなく、決して特別なことではありません。
つまり、あなたが親に対してしんどさを感じているのは自然なことであり、孤独に感じる必要はないのです。
むしろ「自分だけじゃない」「多くの人が同じ悩みを抱えている」と理解することが、気持ちを軽くする第一歩になります。
こちらの記事↓では、親に対して「毒親じゃないけどしんどい」と感じる子どもの違和感について、詳しく解説しています。
親との関係に疲れた心を守るための対処法4選

親との関係において「しんどい」と感じるとき、大切なのは「親をどう変えるか」ではなく「自分をどう守るか」です。
ここでは、心をすり減らさずに関わるための具体的な方法を紹介します。
物理的・心理的に距離を取る
親の言葉や行動で傷ついているのに、それをなかったことのように振るまうと、自分の感情をさらに押し殺すことになります。
そうした状態を続けると、心が疲れてしまうため、物理的・心理的な距離を取ることはとても大切です。
など、できる範囲からで大丈夫です。
親と一緒に住んでいる場合は、生活リズムをずらすなどして、なるべく顔を合わせないようにしてみましょう。
親の言葉をすべて真に受ける必要はありません。
否定的な言葉や過干渉な発言は、軽く受け流すスキルを身につけることが、自分を守ることにつながります。
距離を取ることは“親不孝”ではなく、自分を守る大切な行動です。
境界線(バウンダリー)を意識する
「本当は嫌なのに我慢してやっている」状態は、親との境界線(バウンダリー)が曖昧になっているサインです。
境界線(バウンダリー)とは、自分と他者を区別する心理的な境界線のことです。
バウンダリーは、心理的な距離が近いほど、保ちにくくなります。
親子であっても「自分の問題」と「親の問題」を分けて考えることが重要です。
子どもは、親からの期待に応えようと行動しているうちに、気づいたときには“本当の自分の気持ち”が分からなくなっている場合があります。
親とあなたは別の人間です。あなたが嫌なら、親の期待に応える必要はないのです。
たとえば、
などと、自分の意志を伝えてみましょう。
最初は罪悪感があるかもしれませんが、「NO」と言える練習を重ねることで、心がずっと楽になります。
親にどう思われるかを気にして、すべてを引き受けるのではなく、自分の気持ちを尊重することが、心を守る力になります。
自分の気持ちを整理する
「親といると疲れるのは自分が弱いから」と思う必要はありません。それは自然な反応です。
そんな時は、まず 自分の感情を言葉にして整理することが大切です。
ノートやスマホに、
を書き出すだけでも、自分の気持ちが見えてきます。
言語化することで「これは私の本音だ」と気づけ、親の意見と自分の意見を区別しやすくなります。
「本当はやりたいことがあるのに、どうせ許してもらえない」とあきらめてしまうのは、自分の気持ちをおさえすぎている状態です。
「私はこうしたい」と、あなた自身の思いを優先してもいいのです。
また、「親はこうあるべき」という期待を手放すことも大切です。
親を理想化するよりも、現実の親を受け止めたうえで、自分の気持ちを尊重していきましょう。
サポートを得る
「親といるのがしんどい」なんて、人にはなかなか言えないものです。
世間的には「子どもは親を大切にして当然」という価値観が強いので、ますます自分を責めてしまうでしょう。
そんな気持ちを、ひとりで抱え込む必要はありません。
信頼できる友人に話を聞いてもらったり、同じ経験をした人の体験談を読むだけでも、心は軽くなります。
さらに、どうしてもつらい場合には、カウンセリングや専門家に相談するのも選択肢の一つです。
第三者に話すことで「あなたの感情はおかしくない」と認めてもらえ、安心感が得られます。
心理カウンセリングや相談窓口などを利用するのも、自分を守る大切な手段です。
こちらの記事↓では、「親には感謝しているけど、尊敬はできない」と感じてしまう心理について、詳しく解説しております。
「親といるのがしんどい」関係を変える第一歩
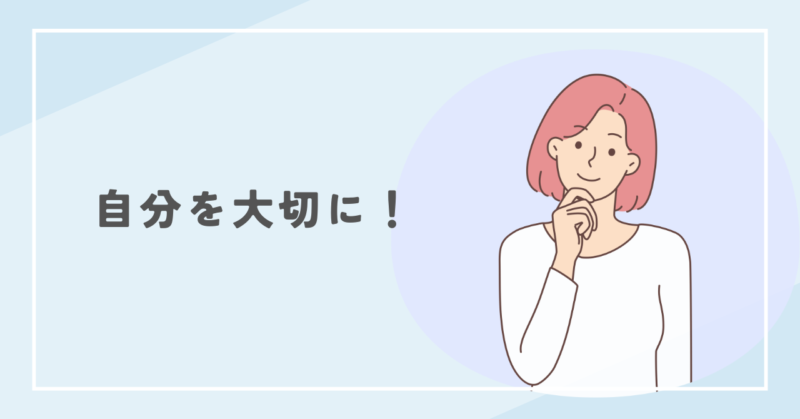
「親を変える」ことは難しくても、「自分の対応を変える」ことは可能です。
そして、自分を守ることは決してわがままではありません。
むしろ、自分の心を整えることで、結果的に親との関係も少しずつ変わっていく可能性があります。
「親だから我慢しなきゃ」と思わなくていい
と、自分の気持ちを押し殺していませんか?
世間では“親を大切にするのが当たり前”といった空気がありますが、心が苦しいほどの我慢は、けっして美徳ではありません。
親子関係は「愛情」と「義務感」が入り混じる、とても複雑な関係です。
だからこそ、「しんどい」と感じるのは自然なことなのです。
むしろ、それだけ頑張ってきた証でもあります。
どんなに親を思っていても、自分が壊れてしまっては元も子もありません。
そのために、少し距離を取ったり、できないことを「できない」と伝えたりするのは、決して冷たいことではないのです。
あなたの心を守ることは、わがままではなく“必要なこと”です。
「常識」よりも「自分の心」を優先していい
世間体や家族の目を気にして、
と自分を責めていませんか?
しかし、人それぞれに合う距離感があるように、親との関係にも“自分にとってちょうどいい関わり方”があります。
親にとっての理想的な子ども像や、世間の「こうあるべき」という常識に縛られる必要はありません。
本当に大切なのは、「どうすれば自分が穏やかに生きられるか」ということです。
もし、親といると心がすり減るなら、距離を取ることは悪ではなく、回復への第一歩です。
逃げることも、沈黙することも、立派な“自分を守る選択”なのです。
これまでたくさん我慢してきたあなたは、これからは「自分の幸せ」を優先して生きていってくださいね。
当サイトでは、毒親や他人を支配する人の対処法などを紹介しております。
人間関係を築くうえでの参考にしていただけたら幸いです。
こちらの記事↓では、親のために自分を犠牲にして生きてきた子どもの末路について、詳しく解説しています。